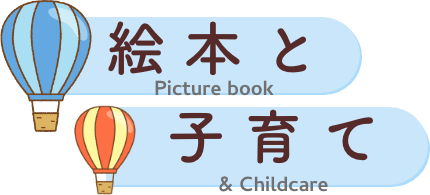1〜3歳児の絵本
成長とともに、いろんな反応を示してくれるようになる時期です。
ストーリー性があったりテーマのある絵本を選ぶようになりました。芸術性のあるものも好んで選ぶように。
どの絵本も私自身が好きになり、親しみをもって読むように心がけました。
ストーリー性があったりテーマのある絵本を選ぶようになりました。芸術性のあるものも好んで選ぶように。
どの絵本も私自身が好きになり、親しみをもって読むように心がけました。

[どこへ いってた?]
作:マーガレット・ワイズ・ブラウン
絵:バーバラ・クーニ 訳:うちだ りさこ
絵:バーバラ・クーニ 訳:うちだ りさこ
色彩豊かな絵本が多いなか、この絵本は黒と赤のみで描かれています。でも、とても丁寧なタッチで可愛い絵に惹かれます。「ねこ ねこどこへいってた?あっち きょろきょろ こっち きょろきょろ ぶらぶらしてた」といった具合に、リスやさかな、ことりなど、おなじみの動物が出てきます。その文体はリズミカルで本質的です。「うま うま どこへ いってた?クローバーのはらっぱ うっとりしてた」こんなシーンもあってステキです。シンプルななかに、深みを感じさせる絵本です。
【マーガレット・ワイズ・ブラウンさんの紹介】
1910年ニューヨーク生まれ。コロンビア大学中退後、バンク・ストーリー校で学び、子どもの本の編集者になりました。優れた画家と組んで実に100作以上の絵本を出版。「幼い子どものための絵本は、すべての感覚にアピールするものでなければならない」というのが彼女のポリシーです。日本では「おやすみなさいおつきさま」「あかいひかり みどりのひかり」などが親しまれていますが42歳の若さで亡くなっています。
1910年ニューヨーク生まれ。コロンビア大学中退後、バンク・ストーリー校で学び、子どもの本の編集者になりました。優れた画家と組んで実に100作以上の絵本を出版。「幼い子どものための絵本は、すべての感覚にアピールするものでなければならない」というのが彼女のポリシーです。日本では「おやすみなさいおつきさま」「あかいひかり みどりのひかり」などが親しまれていますが42歳の若さで亡くなっています。

[はらぺこあおむし]
作:エリック・カール 訳:もり ひさし
この本はとても有名で、開いたとたんカラフルな世界に圧倒されます。生まれたばかりのあおむしはお腹がぺっこぺこ。食べても食べても空腹が満たされません。あげくのはてにはチョコレートケーキやアイスクリームと、考えられないようなものも食べてしまいます。「そのばんあおむしは、おなかがいたくてなきました」でも、また元気になって、こんどはさなぎに。何日も眠ったのち、現れたものは…。この本は途中が仕掛け絵本になっていて、とても楽しめます。
【エリック・カールさんの紹介】
1929年、ドイツ人の両親のもとに生まれました。彼の絵の手法は、ニスを下塗りした薄紙に指や筆で色をつけた色紙を切抜き、貼りつけていくコラージュです。鮮やかな色彩感覚によって「絵本の魔術師」とも言われています。発表した絵本は40作以上にのぼり、39カ国語に翻訳され、出版部数は2500万部を超えています。世界中で読まれているストーリーと絵は、親子で存分に楽しめます。
1929年、ドイツ人の両親のもとに生まれました。彼の絵の手法は、ニスを下塗りした薄紙に指や筆で色をつけた色紙を切抜き、貼りつけていくコラージュです。鮮やかな色彩感覚によって「絵本の魔術師」とも言われています。発表した絵本は40作以上にのぼり、39カ国語に翻訳され、出版部数は2500万部を超えています。世界中で読まれているストーリーと絵は、親子で存分に楽しめます。

[わたしのて]
作:ジーン・ホルセンターラー
絵:ナンシー・タフリ 訳:はるみ こうへい
絵:ナンシー・タフリ 訳:はるみ こうへい
外国の絵本ならではの色彩です。この本の主人公は「手」なので人の顔はでてきません。手を使ってどんなことができるのか、いろんなシーンが描かれています。一番最後は「なかでも、いちばんすてきなのは、わたしのては、ほかのひとのてをにぎれるということ」と締めくくられています。手をずっと眺めたり、動かしたり、口の中に入れてみたり。手っていろんなことができるんだよ、と教えてくれるこの本は、子どもにとっても発見があるのではないでしょうか。「おして たたく。たたくと、ひとをきずつけますね」こんな場面も描かれています。

[ちびゴリラのちびちび]
作:ルース・ボーンスタイン 訳:いわた みみ
とても鮮やかで柔らかなタッチの絵が印象的です。ゴリラの夫婦に生まれた赤ちゃんゴリラの「ちびちび」が、森のみんなに愛されながら、すくすくと成長していく様子が描かれています。「あなたもこうやってみんなに愛されて育っているんだよ」というメッセージが伝わる絵本で、動物たちの「ちびちび」を見つめる目がとても温かくてほっこりします。外国の絵本は絵のトーンや題材が個性的で新鮮ですが、伝わってくるのは同じく子どもへの愛情です。この本も1978年に発行されて以来、長年愛されている絵本のひとつです。
【ルース・ボーンスタインさんの紹介】
ゴリラが大好きだという作者。捕われたゴリラを見るのは悲しいですが、眺めたりスケッチするために、つい動物園に足が向かうそうです。この絵本のアイデアも自然に生まれたそうです。ウィスコンシン大学で美術の学位を取り、幅広い分野で活躍する絵本作家の彼女は、夫と子ども4人とカリフォルニアで暮らしています。「ちびゴリラのちびちび」は彼女の3作目の絵本で、日本では最初に刊行された作品です。
ゴリラが大好きだという作者。捕われたゴリラを見るのは悲しいですが、眺めたりスケッチするために、つい動物園に足が向かうそうです。この絵本のアイデアも自然に生まれたそうです。ウィスコンシン大学で美術の学位を取り、幅広い分野で活躍する絵本作家の彼女は、夫と子ども4人とカリフォルニアで暮らしています。「ちびゴリラのちびちび」は彼女の3作目の絵本で、日本では最初に刊行された作品です。
1
2