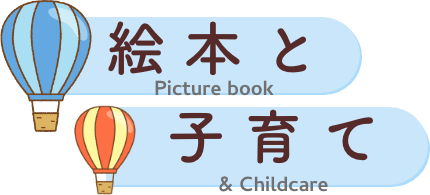4〜6歳児の絵本
落ち着いて読み聞かせができるようになる時期なので、少し長い物語も選ぶようにしました。
一度で読みきらずに、何回かにわけて読むこともできます。
つぎを楽しみにしてくれるような、子どもが興味のある内容を選ぶと飽きずに聞いてくれました。
一度で読みきらずに、何回かにわけて読むこともできます。
つぎを楽しみにしてくれるような、子どもが興味のある内容を選ぶと飽きずに聞いてくれました。

[三びきのやぎのがらがらどん]
作:マーシャ・ブラウン 訳:せた ていじ
ハラハラ、ドキドキが味わえる絵本です。3匹のやぎが山へえさを食べに行くのですが、山へ行くには谷川にかかる橋を渡らなければなりません。橋の下には恐ろしい化け物のトロルがいます。このトロルの描写がすごいのです。「ぐりぐりめだまはさらのよう、つきでたはなは、ひかきぼうのようでした」。1匹目も2匹目もこわごわと橋をわたりました。3匹目にやってきた、大きいやぎのがらがらどんの姿が勇敢でかっこいい。「ひどくしゃがれたがらがら声」という描写があるので私もそのように読んで楽しみました。絵は大胆で荒削り、そして力強いです。こんな表現もあるんだと、絵本の世界の広がりを感じました。

[ともだちや]
作:内田 麟太郎 絵:降矢 なな
子どもの保育園と小学校で題材に取り上げられた物語です。「えー、ともだちやです。ともだちは いりませんか」。森に住むキツネは「ともだちや」をはじめることにしました。友達がほしくて寂しい人に1時間100円で友だちになってあげるのです。果たして、お客さんは…?友達はお金では買うことのできない、大切な存在だと教えてくれる一冊です。大人になると友達に会う機会も減りますが、「友達ってなんだろう」と改めて考えさせてくれる作品です。子どもにも心許せる大切な友達をつくってほしいと思います。

[あおい玉 あかい玉 しろい玉]
再話:稲田 和子 絵:太田 大八
『三枚のおふだ』という昔話がありますが、「おふだ」が「玉」にかわったのがこのお話です。小僧さんが栗拾いに夢中になって日が暮れてしまいました。そこで、山の中の一軒家に泊めてもらうことになったのですが、なんとそこは恐ろしいおにばばの家。知恵を働かせて逃げようとするストーリーもさることながら、描かれている絵が日本の昔話そのもの。おばばが本当に不気味で、どこまでも追いかけてくる臨場感がスリリングです。最後はあっけない幕切れなのですが、そんな話のメリハリも昔話らしくていいですね。

[パンやの くまさん]
作:フィービとセルビ・ウォージントン
訳:まさき るりこ
訳:まさき るりこ
この絵本は個人的にベスト3に入る一冊。パン屋のくまさんが朝早く起きて仕事をはじめる一日が丁寧に描かれています。お店はくまさんだけなので、パンをつくるのも配達するのも、お店番も全部一人。くまさんの仕事ぶりがとても勤勉で礼儀正しくて好感がもてます。くまさんの一日は穏やかで平凡ですが、毎日の仕事をちゃんとして大切に生きるってこういうことなんだと思わされます。子どもには地味な印象の絵本かもしれませんが、私には大切なことを感じさせてくれる深い一冊です。同じ作者で「ゆうびんやの くまさん」「うえきやの くまさん」「ぼくじょうの くまさん」「せきたんやの くまさん」がありますが、この「パンやの くまさん」がダントツの人気だそうです。
1
2